
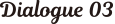 イノベーションを起こすためのダイバーシティとは
イノベーションを起こすためのダイバーシティとは

-
- 岡島 悦子(左)
- 株式会社丸井グループ
社外取締役

-
- 入山 章栄氏(中)
- 早稲田大学
大学院経営管理研究科 准教授

-
- 青井 浩(右)
- 株式会社丸井グループ
代表取締役社長 代表執行役員
丸井グループには、さまざまな職種経験を持つ社員がいます。彼らがグループ会社の中を異動し続けることで、一つの企業の中に多様な背景を持つ、マルチキャリアの組織ができあがります。これが丸井グループのダイバーシティへの取組みであり、その目的はお客さまに喜んでいただくことにあります。イノベーションの専門家である入山氏をお迎えし、当社グループ社外取締役の岡島、当社グループ代表の青井が、丸井グループのダイバーシティへの想いについて語り合います。
成功体験のアイデンティティを打ち破るダイバーシティと職種変更
青井:ダイバーシティや「ワーキング・インクルージョン」を始めたきっかけをお話しすると、私どもは1980年代後半からバブル期くらいまでは時代環境にピタッとはまり短期間で大成功したのですが、バブル崩壊後にとても停滞した時期があったのです。それまで好調だった「若い人、ファッション、クレジットカード」の丸井がアイデンティティ化してしまい、そこを打ち破った新たな創造をすることができなくなっていました。当社には約30の店舗がありますが、180度ひっくり返したビジネス転換を始めたところ、比較的導入階に近い雑貨売場では、すぐに品揃えの変更や接客の仕方に変化が起きているのに対して、上層階の紳士服や子供服、スポーツ用品売場は変わることができなかったのです。「なぜ?なぜ?」と考えていったら、変わることができなかった所は我々にとって強みのある売場で、販売員も10~20年「この道一筋」でやっていた売場でした。これに対して雑貨売場は、新入社員の登竜門だったため、人の出入りが頻繁にありました。経験が長くなると成功体験がアイデンティティ化されるのであれば、すべての売場で同じ条件で人が異動する仕組みをつくれば、イノベーションが起こりやすい組織になるのではないかと思ったのです。それがダイバーシティであり、当社の職種変更が始まったきっかけです。
岡島:この5年間で職種変更者は全社員の約34%とすすんでいますが、スタート当初はそれまでの経験や知見が通じない他の部署に行ったら、せっかく積み上げてきた評価が落ちてしまうのではないかという声もありましたね。
青井:最初はみんなそれまでの自分のキャリアを否定されたような感じになって心配したのですが、慣れてきたら新たな職場でそれまでの経験がむしろ役に立つということがわかり始め、逆に異動しないと取り残されたような雰囲気になってきたのです。
入山:その時にはランダムとは言いませんが、意外と大胆な配置換えをしているのですか。逆に言うと、非常に大胆な変化、この人をこういうところに動かしましたという事例はありますか。
青井:直近では2人の常務執行役員の異動です。それぞれ小売セグメント責任者と金融事業責任者だったのですが、担当事業を入れ替えました。
入山:そういう大胆な配置ができるのはすごいですね。小売の人がカードに行ったり、カードの人が小売に行くというのは面白いですね。プラスは絶対にありますよね。
イノベーションとは「知と知の組み合わせ」から生まれる
入山:いろいろな人が動くことがイノベーションにはとても重要だと思っています。イノベーションの本質は結局、新しいことをやるということです。新しい考えやアイディアは「知と知の組み合わせ」から生まれてくるのです。今までつながっていなかった知と知が新しく組み合わさることで、新しいアイディアが生まれるわけです。ただし、人間の認知には限界があります。同じ業界にいて、それこそ同じ売場に何十年もずっといると、その世界しか見えなくなり知の組み合わせが終わってしまうのです。そのため新しい知と知を組み合わせるには、遠くの知を見て組み合わせるという「知の探索」が重要になります。一番手っ取り早いのは、バラバラの知見・経験・価値観を持っている人々が、一つの組織に集まるということです。そしてもう一つが、「イントラパーソナル・ダイバーシティ」です。例えば私と岡島さんが一緒にいて、新しい知が組み合わさるということだから、本質的にはこれも同じダイバーシティなのです。一人の人間が多様な経験を持ったマルチキャリアであれば、それ自体が知と知の組み合わせになるのです。ダイバーシティとは、イノベーションのためにやるものだと私は理解しています。
岡島:そういう意味で言うと、丸井グループの職種変更は個人の中の多様性、いわゆる「イントラパーソナル・ダイバーシティ」を高めるのにとても重要。お客さまと一緒に何かをつくっていく時に、こちら側に引き出しがたくさんあるということが効いてくるということですよね。
青井:4年前くらいに岡島さんと女性活躍という意味でのダイバーシティを強化していた時、まさにそれだと思ったことがあります。男女のダイバーシティも大切ですが、イノベーションという意味ではさまざまなキャリアや視点を身につけていくために、もっと掛け合わせでやっていく必要があるのではないかと言ったら、岡島さんが「それって個人の中の多様性ですよね」と。現在の丸井グループは多様性を「個人の中」「男女」「年代」の3つですすめています。
入山:「イントラパーソナル・ダイバーシティ」には、さらにプラス効果があります。多様な経験を持ったマルチキャリアの人は、自身が多様な経験をしているため多様な人を受け入れ、よりインクルーシブになれるのです。もう一つは「プロソーシャル・モチベーション」と言いますが、他者視点を持ちやすくなるということです。他者視点を持つことは、クリエイティビティにとってとても重要です。
青井:確かに、我々のような小売とかサービス業をやっている人には、人が好きな人が多いのです。人に喜んでいただくことにやりがいを感じる人が多くて、相手に共感する力、エンパシーが強い人が多いようです。自分はともかく、お客さまはどういう気持ちなのかが先に立つのです。
岡島:このことは丸井グループ全般に言えることです。「お客さまがどう考えるか」「お客さまと共に」が標語になっているだけでなく、役職が上の人も「若手がプランニングするなら、私たちがサポートします」「それはお客さまのためにいいね」という発想につながるのです。他者への想像力。お客さまを共通起点としているからこそ、他者への想像力と受容性を持てていますね。
青井:若い人たちの感性とか考え方を活かしていくためには、年代の多様性がとても大切だと思っています。若い人を前面に立てて活躍してもらうということは、これまで上に立って指示・命令していたマネジメント層が、彼らの後ろに回って支援するサポーター役になるのです。うくいくかどうか心配だったのですが、岡島さんが言ったように「私たちは元々人を育てるのが好きだから、私たちは応援に回ります」ということで意外とすんなりいったのです。
岡島:たとえ役職や役割が逆転したとしても、「これは役割だよね」と平気で捉えているように見えます。それは「お客さまのために」という想いと理念の浸透があるからなのです。
業態という「名詞」から、使命による「動詞」へ
岡島:丸井グループが面白いのは、ジョブ型というよりメンバーシップ型であることです。ファッションや販売というジョブ型より、丸井グループに属し、お客さまに価値を提供したいという丸井グループへの帰属、メンバーシップ型が強いのが特長です。今では店舗でのファッション比率が3割を切る形になっていても、「もうファッションができないなら辞めます」といったことがないんですよね。
青井:ビジネスモデルを変えることは、ある意味、「えいや!」でやればできるのですが、ビジネスモデルを実際に動かして価値を生み出す部分は人がやりますので、人の心がそれについていかないと絵に描いた餅になってしまいます。過去の成功体験がアイデンティティ化していた時代は、ファッションが好きで入ってきた人がとても多かったので、一回立ち止まって、そもそも何のために会社に入ったかを振り返ってみた時に、最初はファッションが好きで入ってきたけれど、あの時にこういう接客をしてお客さまから「ありがとう」と言われたとか、異動する時に花束をいただいたとか。それは、お客さまのお役に立てることが嬉しいのであって、それをもっと活かしていくためには例えば新しいことにチャレンジするのもあるよねと、みんなで話し合いながら現在の形までやってきたのです。
入山:経営学には「腹落ちする」という意味の「センス・メイキング」という考え方がありますが、とにかく長期ビジョンがあり、「この会社は何のための会社であるか」が明確にあって、それを語ってみんなで腹落ちするというものです。それがないと人は変わらないし動かないのです。「丸井という会社は何を提供する会社なのか」をもう一度問い直したことで、長期ビジョンのようなものが出てきて、「それなら別にファッションでなくてもいいよね」と。小売とかファッションとかカードとか、そういうことではなくて、お客さまを喜ばせる会社。やはり名詞ではなく動詞ですよね。小売とかファッションとかカードとかという名詞は変わるかもしれませんが、「お客さまを喜ばせたい」という動詞は変わらないのではないですか。
青井:私もよく「丸井は小売業ですか、金融業ですか」と聞かれて。あまりによく聞かれるので、2017年の共創経営レポートの表紙に「私たちは両方です」と明記しました。私たちは、そういう形とか名詞にこだわっているのではないのです。
岡島:今後入社してくる学生さんも、実は知っている職業のメニューは限られている。業種や職種をいろいろやらせてもらう中で「私は意外に金融が好きだったんだ」と気づくということもあるでしょうね。
入山:丸井はお客さまを笑顔にしたい会社だということですよね。何業とか扱う商材はどうでもいい。だからアニメビジネスも始めたわけですね。
青井:世の中から見ると、私たちの職種変更は転職のような感じですが、グループ一括採用の社員というセーフティネットの中で、いろいろ違うことが経験できるのです。さまざまな職種を体験しながら変化を楽しみ、企業としても人としても、お客さまに笑顔になっていただくために成長していけたらいいと思っています。
入山 章栄氏
早稲田大学 大学院経営管理研究科 准教授
慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。株式会社三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米国ピッツバーグ大学経営大学院でPh.D.を取得。同年より米国ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年より早稲田大学 大学院経営管理研究科 准教授。専門は経営戦略論、国際経営論。2012年に出版された著書『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)はベストセラーとなり、現在は「ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー」誌上にて長期連載「世界標準の経営理論」を掲載するなど、各種メディアでも積極的に活動している。
ステークホルダーとの対話
このサステナビリティサイトは、色覚障がい者の方々に配慮しています。







